

諏訪、茅野から国道20号を南下、山梨県との境の手前となる上蔦木交差点を左折して信濃境駅の方に登って行くと井戸尻考古館の案内表示があります。
平安時代末期に人、動物を擬人化して書かれたとされる鳥獣戯画が日本最古の漫画とされますが、井戸尻土器の絵こそ日本の漫画のルーツのような気もします。
通常の石匙は片刃ですが、両刃もあって引っ掻いて使うのではなく、裁断に使ったのではないか、除草に使ったとも考えられ、また広幅の打製石器も多くあることなどから農具としての石器ではないかと藤森栄一氏は考え縄文農耕論を唱えるに至った遺跡でもあり、今日、井戸尻考古館では石器を体系的に整理し、農作業があったとしています。
右は蛙の目が対になっているとされる双眼五重深鉢土器(高さ57cm)です。藤内遺跡から出土した縄文時代中期中葉(約4700年前)のものです。口縁はミミズクということです。内部も5重のリングなっていて、蓋を落して蒸かすことができる土器です。5段の周囲には何やら不思議な文様か絵文字がありますが、月の満ち欠けに関係すると考えられています。

蛇を戴く土偶は、土偶としては珍しく頭頂にとぐろを巻いたような蛇があり、3つの孔があります。発見者の一人によって「巳(へび)をいただき神子(みこ)と名付けられ、重要文化財になっています。

当考古館を訪ねた時は冬で事前に電話した折に館内は寒いので防寒対策をして入館するようにアドバイスをもらっていましたが、アドバイスの通りにとても寒い館内でした。しかし、数々の遺物に興奮するほどに見応えのある内容の展示です。著名な考古学者戸沢充則氏が井戸尻文化と唱えるだけのことはあります。
縄文時代中期中葉の藤内遺跡で出土した石器の半分以上は打製石器で、そのことから縄文農耕論が出てきます。その形状から土堀具の石鍬と考えられており、現在の鉄の鍬と並べて展示されています。
石器に木製を番えて、高度な道具を完成させています。


右は1984年に藤内遺跡から出土した円筒形の土器に神か人の像が抱きつくように造形されている神像筒型土器です。口縁の頭は中空で、髪は左右に分けてあるかのようで、型は逆三角形、土器を抱くように腕の付け根から肱の関節のところが非常に高く盛り上がって、それから土器の壁にへばりつくように平たくなっています。下半身の造形はない。眼は正面のが左眼、縦方向の空孔が右眼で、目じりは蕨手状に巻いています。まるで宇宙人のような神です。
この半人半蛙(はんじんはんあ)有孔鍔付土器(高さ51.7cm)ですが、平らな口唇部と口縁部に隆起した鍔があり、20数個の孔のあることから用途として醸造説、太鼓説、種子壺説、鳥の羽をさした装飾説などあります。手を拡げた人のようでもあり、カエルのようでもあり、カエルの左右に蛇があります。トンボ眼鏡のようでもあります。全体を精選された土を使い赤色に塗っており、他に見られない形でもあり、単なる深鉢ではなさそうです。
しかし、蛇や蛙、オオサンショウウオ、うさぎ、鳥など多くのキャラクターが登場する土器は同じ八ヶ岳山麓の出土品とは、また異なる世界観や美的感覚を感じることができます。

井戸尻の土器は砂が1/3混じり土も精製され、極めて細かな砂と土が使用されています。幾層かの土のなかから適した材料となる粘土を選び、何代にもわたって伝承されてきた混合する混和剤の材料と比率で作った生地を寝かせ、ひも状に輪積みして、形作り、水が漏れないように内側を徹底的に押しつぶして磨きながら、器の乾き具合で文様をつけると言います。
破損した土器の出土は少ないそうで、この遺跡群には熟練した技を持つ人々がいたと想像されます。
井戸尻の土器は煮炊きをする器としては実用性に乏しいものが数多くあります。自然界に畏敬の念を持って生活していたようで、不思議な造形美です。見学したのが、2月で、見学者が少ないこともあって、まったく暖房のない寒い館内でしたが、見学するとそれを忘れてしまうような展示です。隣には富士見町歴史民族資料館が併設されていて、有史以降のものが展示されています。


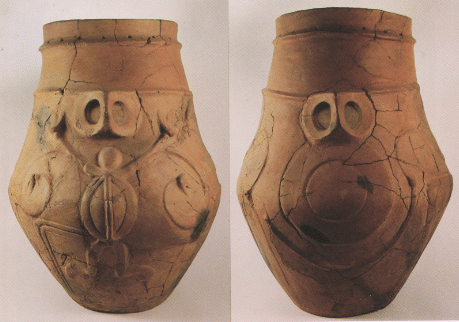

井戸尻考古館には、富士見町内から出土し縄文中期の標識土器の名前となっているほどの土器が多く展示されています。約2.5kmの長さの範囲で縄文中期後半の曽利、中期前半の井戸尻、藤内、初頭と前半の間の新道、狢沢、中期初頭の九兵衛尾根のものなどです。
東京への帰路、中央自動車道の釈迦堂パーキングレエリアから歩いて釈迦堂遺跡博物館に寄り、土偶を見て戻ることとしました。

1961年に曽利遺跡からの出土した高さ43cmの水煙渦巻文土器は底部が平で、胴部は円筒形で半截竹管文(はんざいちくかんもん)という竹を半分に割ったような隆起した文様が描かれ、口縁は炎か水ような渦の文様でエネルギーを感じます。
信州川流域には火焔式土器と称するものが多く出土していますが、これはサケ・マスが遡上してくる水しぶきの様子を感じる逸品で、郵便はがきのの料額面に陰影として採用されています。豊かに暮らす女性が制作したのではないでしょうか。器具本来の煮炊き用には使い難そうに思えますが、美術品としては完成度の高いものを感じてしまいます。
左は中期前半の藤内遺跡から出土した半蛇半蛙(はんあ)文深鉢です。
八ヶ岳西麓の博物館の遺物などを見て、改めて日本人の持つ独特の世界観、精密な加工技術、モノ造りへのこだわりといった精神の基層が1万年に亘る縄文時代に形成され、それが特に強くこの地域に住む現代人に引き継がれている思いがしました。